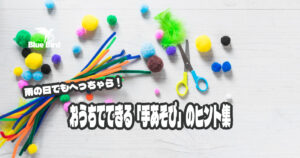「できない」はダメじゃない。
はじめに
私たちがこの場所に「Blue Bird(ブルーバード)」という名前をつけたのには、ちょっとした願いが込められています
“幸せの象徴”——それも、もちろんあります
でも、本当はそれだけじゃないんです
私たちが大切にしたいのは、
「自分のままでいい」
「できないことがあっても大丈夫」
そう心から思えること
子どもたちが、自分をまるごと受け入れて生きていけること
それこそが、私たちの支援のゴールです
■ 「できない」はダメなこと?
答えは、はっきりNOです
大人にも子どもにも、「できること」も「できないこと」もある
それは、とても自然なこと
そもそも、私たちの社会は、誰かの「できない」を、誰かの「できる」で補い合って成り立っています
助けたり、助けられたり。支え合うことが前提の世界ですよね
でも、子どもたちは、まだその仕組みを知りません
だから、「できない」ことがあると、不安になったり、つい自分を責めてしまったりします
■ Blue Birdが目指す
“自己受容”というステージ
私たちが目指しているのは、「全部できる子になる」ことではありません
✔︎ 「これが自分だ」と認められること
✔︎ 「できないときは、助けてって言っていい」と思えること
✔︎ 「できること」と「できないこと」がある自分を、そのまま大切にできること
これが、私たちが大切にする“自己受容”というステージです
Blue Birdは、子どもたちがそのステージに立てるように、そっと背中を押す存在でありたいと願っています
■ 支援の本当の目的
私たちの支援の目的は、
「全部できるようになること」ではなく、
「困ったときに、どうするかを知ること」
✔︎ 苦手でもいい。自分なりのやり方がある
✔︎ 誰かに頼っていい。「助けて」が言える
✔︎ 「ひとりじゃない」と感じられる
だからこそ、私たちの支援は、子どもに「がんばらせる」ことが目的ではありません
「一緒に考える」「工夫する」「助け合う」——それが基本のスタイルです
■ 大人ができること
子どもたちに伝えたいこと
それは、
「できないって言ってもいいんだよ」というメッセージ
そして、
「どうしたい?」「どうしたらできそう?」を、焦らず一緒に探していくこと
大人が「できない」に寄り添うことで、子どもたちは、「じゃあ、こうやってみようかな」と、自分の力で前に進んでいけるようになります
■ 最後に
私たちにとって、Blue Bird=自己受容のステージ
もちろん、「できることが増える」のは素晴らしいこと
でも、もっと大切なのは、
「できない自分」を責めるのではなく、
「それでも私は私」と思える力。
私たちは、子どもたちが、
「これが私のBlue Bird」
と胸を張れるような未来を、一緒に育てていきたいと思っています
【おわりに】
このメッセージが、Blue Birdの想いや、私たちの支援のカタチを知ってもらうきっかけになれば嬉しいです
もし、共感してくださった方がいたら、
ぜひ一度、私たちに会いにきてくださいね