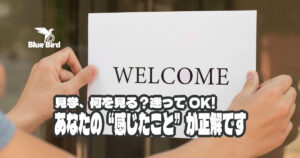診断名がつかないと支援は受けられないの?——その疑問に答えます
診断名がつかないと支援は受けられないの?——その疑問に答えます
「ちょっと育てにくさを感じる…」
「発達が気になると言われたけれど、診断はまだ」
「支援を受けたいけど、うちの子には診断名がついていない…」
そんなとき、
「診断されないと支援って受けられないの?」と不安になること、ありませんか?😟
今回は、そんな疑問にお答えしながら、
🌱診断がある・ないに関係なく、その子に合った支援を考えることの大切さについてお話しします
■ 🩺 そもそも「診断名」って何のためのもの?
診断とは、医師などの専門家が
🔍「その子の特性や傾向」を理解しやすくするために行うものです
診断名がつくことで、
・医療や福祉サービスを使いやすくなる
・特性に合わせた支援の方向性が見えてくる
・まわりに説明しやすくなる
…などのメリットがあります
でも、だからといって
📌“診断がついていない=支援が必要ない”
ということではありません
■ 👶 まだ小さいうちは診断がつかないこともあります
実は、発達に関する診断名は
👶幼児期にはつきにくいこともよくあります
年齢によって発達のスピードに個人差が大きく、
「まだ経過観察の段階」や「グレーゾーン」とされることも多いからです
でも、困っている “今” に支援が必要かどうかは、
診断の有無だけでは判断できません
困っているのは “診断名” ではなく、目の前の「その子自身」だからです
■ 🧩 診断がなくても受けられる支援、あります!
たとえば私たちのような
児童発達支援事業所では、診断名がついていなくても、
⏩「発達に気になる点がある」
⏩「日常生活で困りごとがある」
といった場合に、支援を受けることができます
実際に利用されているご家庭の中にも、
「診断はないけれど、専門的なサポートがほしい」
「子どもに合った関わり方を学びたい」
という思いで通っている方がたくさんいます🤝
大切なのは、「支援を受ける資格があるか」ではなく、「支援が必要かどうか」なんです
■ 🗣️ 相談からスタートしてOK!
「診断がないから、まだ相談しちゃいけないのかな…」なんて思わなくて大丈夫
まずは話してみることで、今の状況を整理できたり、適切な支援の情報を得られたりします
✅ 子どもがよくかんしゃくを起こす
✅ ことばの発達が心配
✅ 集団が苦手で園でうまく過ごせない
✅ 友だちとトラブルになりやすい
…こういったお悩みも、立派な「支援を考えるきっかけ」です
■ 💡「診断名」は、“その子を知るためのヒント” のひとつ
もちろん、診断があることで使える制度や手続きもあるため、必要に応じて医療機関と連携することもあります
でもそれは、「その子のための手段」であって、
📍ゴールではありません。
私たちが一番大切にしているのは、
“いま目の前で、困っているこの子” に、どんな支援が必要か?という視点です
🌷 最後に
「診断がないから、動けない」ではなく、
「気になっていることがあるから、今できることを探す」——
その姿勢が、
🌱お子さんの安心や成長につながっていきます
支援は、“誰かに認められてから” 受けるものではなく、
「この子にとって必要だと思ったその瞬間から」受けていいんです
あなたが感じている小さな違和感や不安
それはきっと、大切なサインです
ひとりで抱えず、ぜひ一緒に考えていきましょう