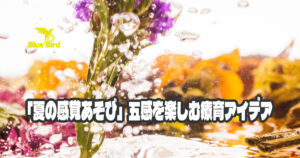診断はゴールじゃない——“この子の幸せ”のためにできること
🧭 診断はゴールじゃない——“この子の幸せ” のためにできること
「〇〇の傾向があるかもしれません」
「一度、専門機関での診断を受けてみては?」
そう言われたとき、親としてどんな気持ちになるか……
😟 不安、😣 ショック、😕 戸惑い、😔 抵抗感
そして同時に、「もしそうだったら、何ができるんだろう?」という思い
今回は、そんな “診断” という出来事をどう受け止め、どんなふうに「その子の幸せ」につなげていくか、少し立ち止まって考えてみたいと思います
■ 🩺「診断を受ける」ってどういうこと?
私たちの事業所にも、
「発達がゆっくりかもと言われて…」
「診断名がついたけれど、どう関わればいいか分からない」
というご相談が多く寄せられています
まず大前提として伝えたいのは、
👉 診断は “ラベル” ではなく、“理解のヒント” だということ
診断名そのものが、その子を決めるわけではありません🙅♀️🙅♂️
たとえば「ASD(自閉スペクトラム症)」とひとくちに言っても、表れ方は本当にさまざま
「こういう特性がありそう」と分かることで、💡接し方や🛠️環境の整え方が見えてくるーーそれが“診断”の役割のひとつです
■ 🏁「じゃあ、診断がついたら終わり?」…ではありません!
診断を受けたことで、必要な支援や制度の利用ができるようになることもあります。
でもそれは、
📍「その子の支援人生のスタートラインに立った」
というだけ
本当に大事なのはここからです
診断があってもなくても、私たちが見ていくべきは
🌱「この子が、日々どんなことで笑い、何につまずき、どんなふうに人とつながっていくか」
それは診断名だけでは分からない、“この子自身の姿” です
■ 👀大切なのは、「診断名」よりも「この子のまなざし」
私たちが支援を考えるとき、いつも心に置いている問いがあります
この子は、いまどんな気持ちなんだろう?💭
どんな未来を描いているだろう?🌈
どんなふうに関わってもらえたら、安心できるだろう?🤝
子どもたちが笑ったり😄泣いたり😢、ぶつかったり甘えたりする日々の中に、
その子なりの “生きづらさ” も、“希望の芽🌱” も、たくさん詰まっています
それを見つけ、寄り添い、一緒に歩いていく🚶♀️🚶♂️
それこそが、診断を超えて目指す「支援」だと思っています
■ 🤔「この子の幸せのために、いま私にできることは?」
もしかしたら診断は、少し勇気がいることかもしれません
でも、それはその子の特性を “責めるため” のものではありません
むしろ、
🔍「この子らしさ」に光を当てて、
🌟 よりよく関わっていくための地図のようなもの
そして私たち支援者にとっては、
📌診断だけに頼らず、“いま目の前のこの子” をちゃんと見ていくことが、
何よりも大切だと感じています
🍀 最後に
子どもたちの幸せって、
きっと「できるようになったことの数」では測れません
たとえ苦手なことがあっても、
🌼 自分らしく過ごせて
🤗 大切に思ってくれる人がいて
😄 笑える時間があること
それが、“その子の幸せ” なのだと思います
私たちは、そんな日々の一歩一歩に、
そっと手を差し伸べられる存在でありたいと願っています